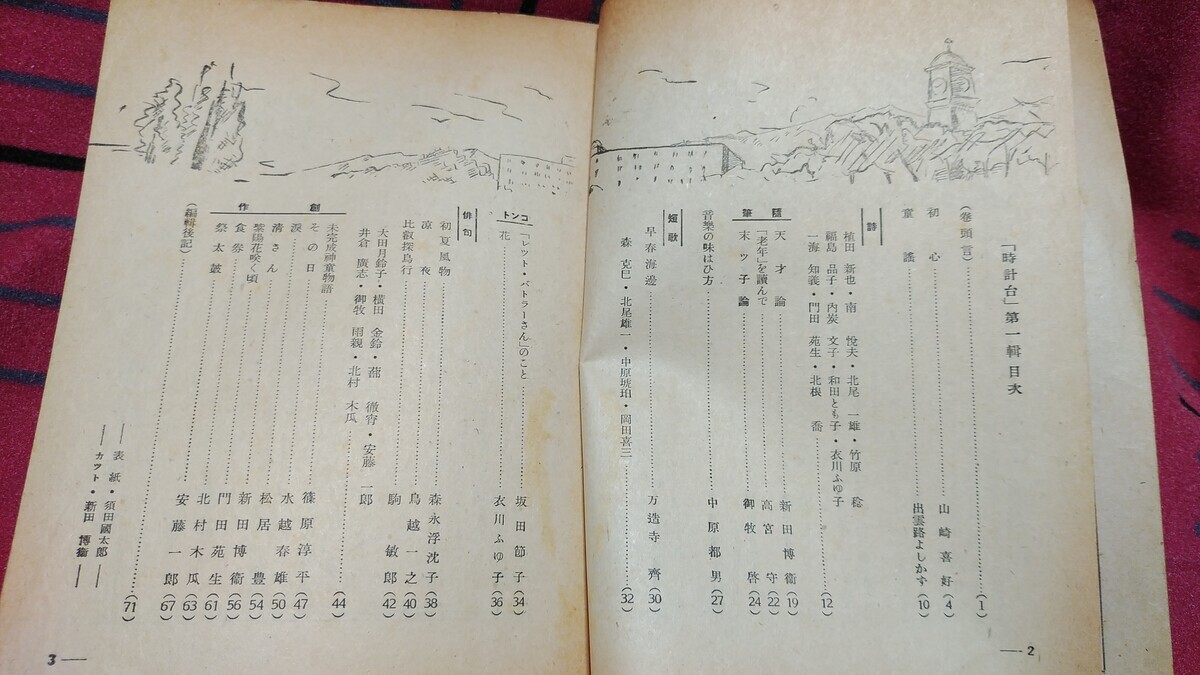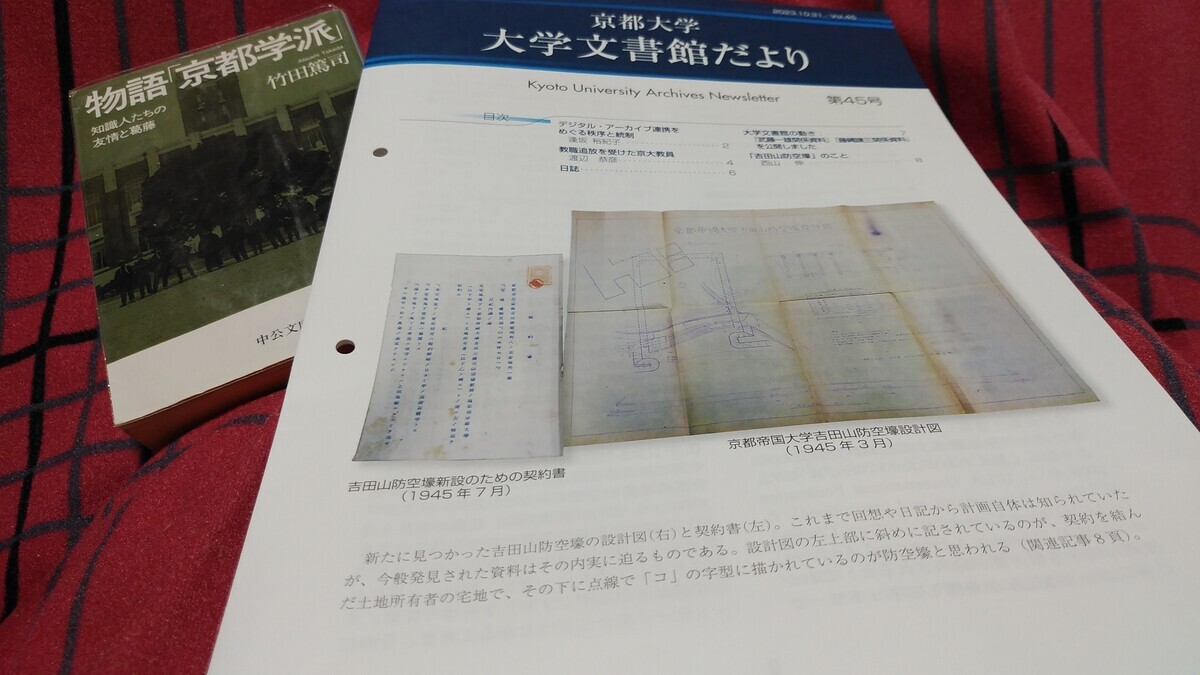『大佛次郎随筆全集第3巻』(朝日新聞社、昭和49年2月)中「未刊随筆」として、「美人の町」が収録されている。ここに、真山美保が出てくる。
(略)真山美保は、真山青果の遺児で、日本全国のいなかを回って理想のある芝居を見せて歩いている特志の女性である。その仕事に生涯をかけているのだ。父の死後、妹さんと私の家に訪ねて来たこともあって、若い日から知っている。(略)
この美保が妹と大佛を訪ねたことは、昨年8月に刊行された大佛次郎記念館編『南方ノート・戦後日記』(未知谷)で確認できた。
(昭和二十二年)
四月四日
(略)真山青果の娘たち二人来訪。姉は民衆座とかで芝居をしてゐるさうである。現在は東京に小屋なく電燈のない農村へ行くこともあるさうである。
『近代文学研究叢書第64巻』(昭和女子大学近代文化研究所、平成3年4月)によると、青果の長女美保は、昭和22年入団した新協劇団を25年に中堅俳優8人と共に離脱してヴェリテ・せるくるを結成している。大佛の日記中に「民衆座」とあるのは、「新協劇団」の間違いなのだろう。青果と大佛の関係は、不明である。星槎グループ監修、飯倉洋一・日置貴之・真山蘭里編『真山青果とは何者か?』(文学通信、令和元年7月)の「交友録1」に挙がる青果の住所録(昭和19年)に載る人名の例示には含まれていない。なお、南木芳太郎の名が見える。
青果の日記の翻刻が続けられていて、国文学研究資料館調査研究報告44号に青木稔弥・内田宗一・高野純子・寺田詩麻「[翻刻]青果日記(昭和三年・昭和五年)ー眞山青果文庫調査余録(四)ー」が掲載された。→「国文学研究資料館学術情報リポジトリ」
早速読むと「孚水画房」が出てきた。
(昭和三年五月)
二日 (略)
(略)湯に行きたる留守に、孚水画房(本郷区湯島同朋町一五)元禄版画集第二を置いてゆく。永見君の紹介なるよし。
(略)
二十九日 (略)
(略)
浮世絵商孚水画房なる者来る。春画巻物を出す、叱る。
永見徳太郎君より五島スルメ(略)
孚水画房が春画を見せて叱られてますね。紹介した「永見君」は永見徳太郎と思われる。「書肆夏汀堂永見徳太郎の葉書ー長崎県美術館で「浪漫の光芒 永見徳太郎と長崎の近代」展開催中ー - 神保町系オタオタ日記」で紹介した人物である。孚水画房の店主金子孚水についても、「島田筑波と春峰庵事件の金子孚水による『孚水ぶんこ』ーー若井兼三郎の蔵書印「わか井をやぢ」についてーー - 神保町系オタオタ日記」で紹介したところである。問題多き人物だが、『真山青果とは、何者か?』の「『真山青果全集』をめぐる人々」によると『真山青果全集第15巻』(昭和16年12月)に収録された『随筆滝沢馬琴』の図版提供者の一人として名が見える。金子が昭和7年5月に創刊する『孚水ぶんこ』の編輯人島田筑波については、「『調査研究報告』41号(国文学研究資料館)の「眞山青果文庫調査余録」に神保町系オタオタ日記 - 神保町系オタオタ日記」で言及したところである。今のところ翻刻された日記には登場していないが、いずれ登場するだろう。
青果に関する資料を送っていただいた青田寿美先生の追悼として、『近代出版研究』3号(皓星社発売)に「明治期における裏表紙のパブリッシャーズ・マークに関する一考察」を書きました。生前全然お返しができませんでしたが、ささやかなお返しとして天国に届きますように。